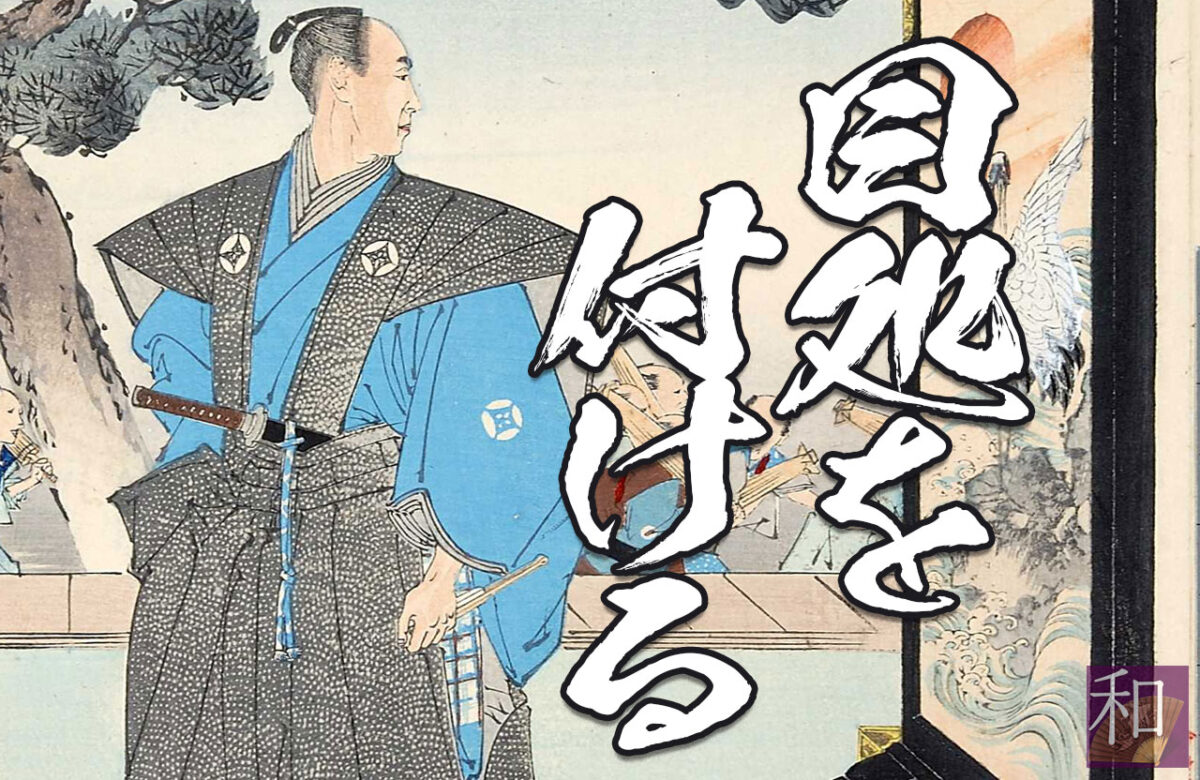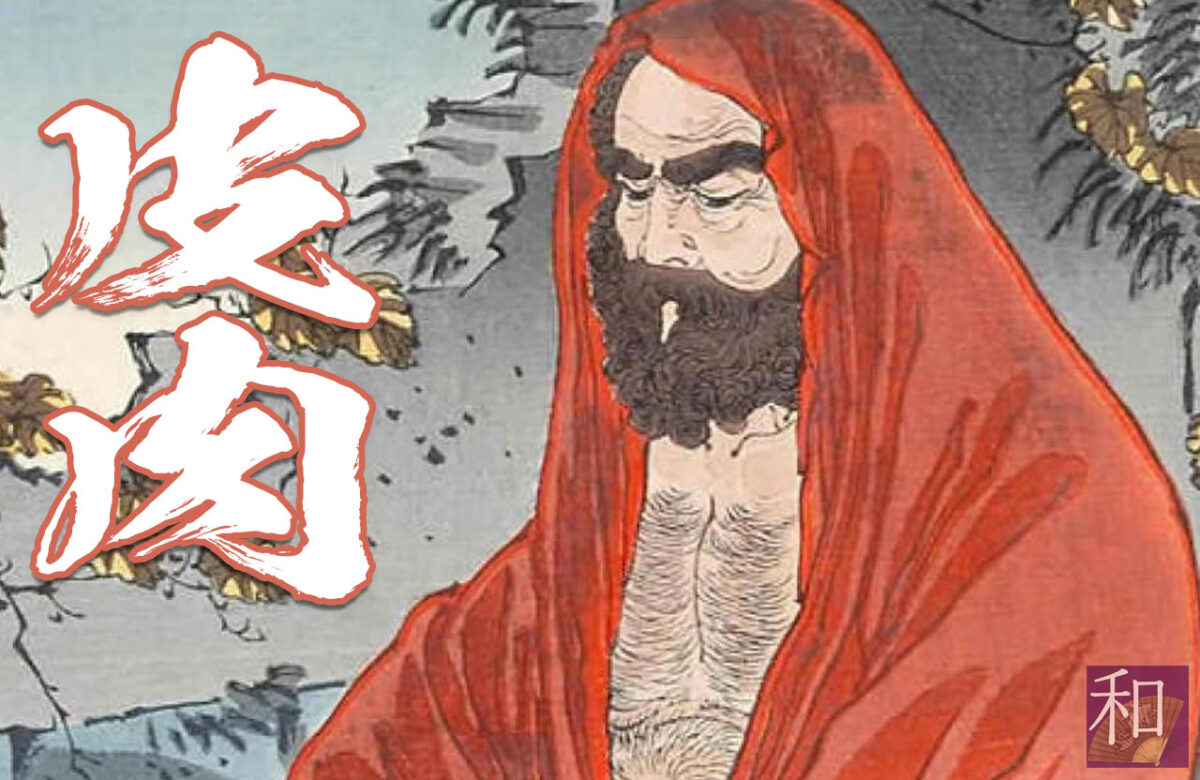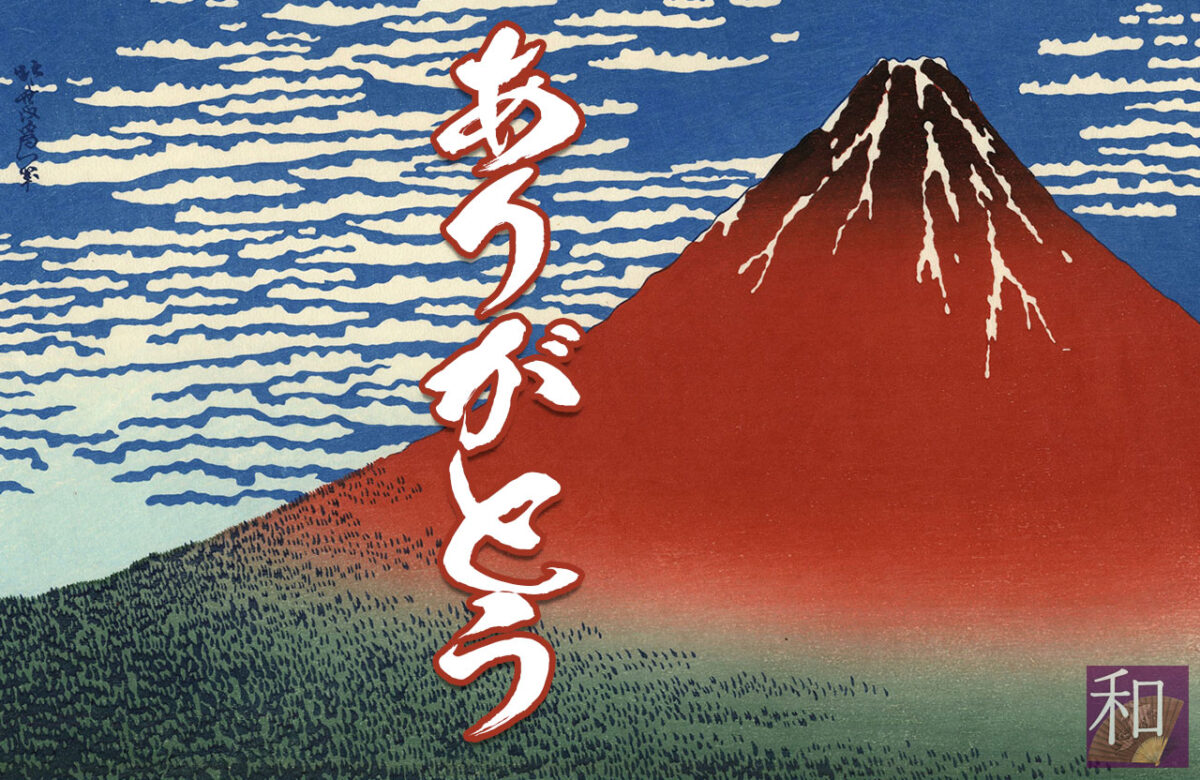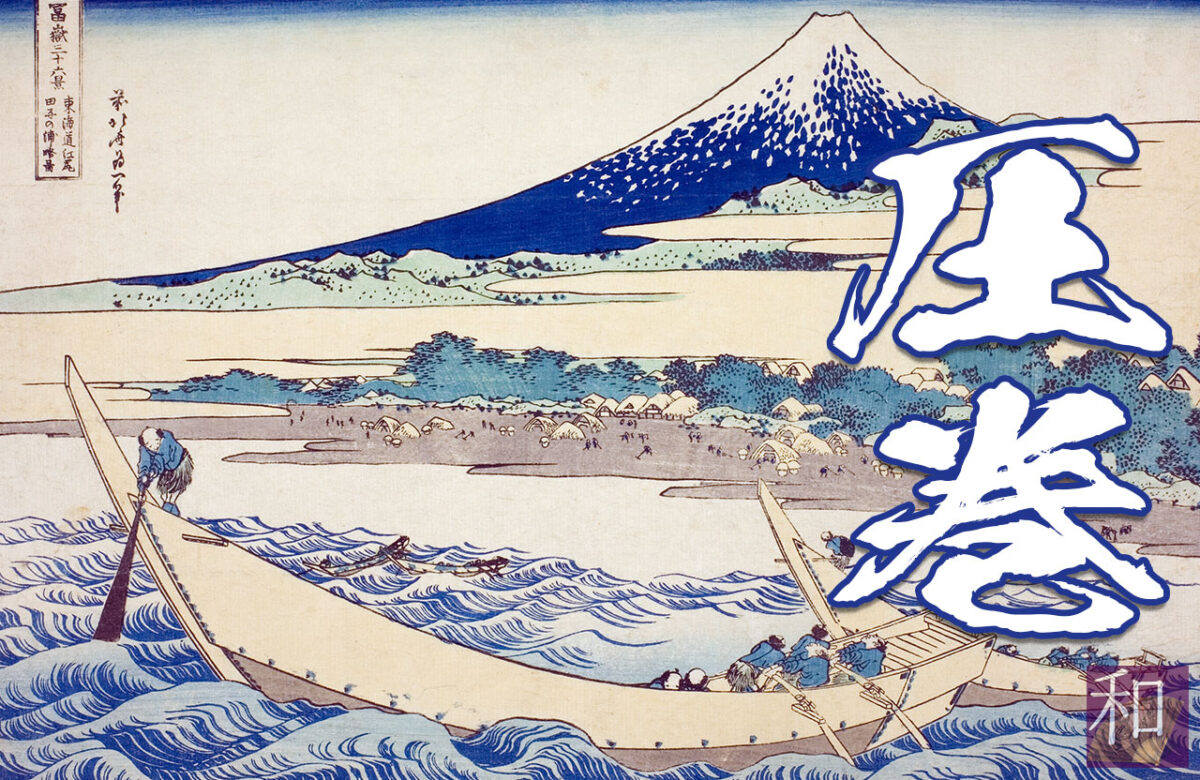日本語と語源– category –
-

神社で御神酒が奉納される理由
御神酒は、神道における神事の一環として奉納されます。神社によっては、毎日の祭儀で御酒を供える場合もありますし、特別な祭りの際にのみ御神酒を供える場合もありますが・・・ -

「うやむや」は事実から背を向けたい悪人の方便?
犯罪がわからないように証拠をうやむやにするとか、起きた事実をうやむやに無かったことにして逃げるとか、「うやむや」という言葉は悪人の方便のような気がします。さらに私は自分の非を素直に認めず、事実をうやむやにして逃げる人を軽蔑します。 -

日和見主義、小春日和の「日和」とは?
日和という言葉には、のんびりしたのどかな印象を与えます。その印象を天候に例えたり、人格に例えたり、様々に使える便利な言葉です。この日和という言葉にはどんな意味が含まれているのでしょうか? -

困難に直面しても「火中の栗を拾う」意味とは・・・
「火中の栗を拾う」という言葉は、危険や困難を冒して得ようとすることを表す日本の慣用句です。他人がやりたくない、またはできないような危険な仕事や困難な状況に対して自分自身が挑戦することを指します。でもこの場合の行動は失敗に終わるケースがほとんどだと言われています。それはなぜでしょうか?この言葉の由来が説明しています。 -

「目処を付ける」の意味と使い方
例えば仕事に一区切り付けることを目処を付けるといい、目標設定をする際にも何日までに目処をつけようといいます。この目処をつけるという言葉にはどんな由来があるのでしょうか?リモートワークでなかなか仕事の区切りがつけられないリモートワーカーにおすすめしたい言葉ですね。 -

自暴自棄とは?偉人も奇行に走る
自暴自棄とは自分自身や自分の人生に対して無力感や希望を失い、何もかも投げ出してしまうことを指します。自暴自棄になって自らの立場を失い滅亡した人物は、歴史を振り返ればたくさん存在します。人はなぜ自暴自棄になってしまうのか? 予防する方法はあるのか? -

「皮肉」は奥ゆかしき日本人の嫌味
面と向かっては言い難い嫌味を相手に通じるか通じないかのギリギリの言葉を発することは、日頃謙虚さを大事にしている私も言いたくなることがあります。 それを皮肉といいますが、その語源を探ってみると -

奇跡の日本語「ありがとう」は国を豊かにする
「ありがとう」の語源は?困難が解決したときや、思わぬ幸運にあった時の感慨は深い。そこで、やがてそういう時の、かたじけない、もったいない、恐れ多いという気持ちを「有り難し」と言い換えるようになったのではないでしょうか。 -

畳が愛される理由と畳の需要
最初は今のような厚みのある畳ではなくて、稲藁やイグサを編んだ敷物で薄縁(うすべり)というものでした。古代まで遡ると、ござ、むしろなども「畳」の仲間です。畳に関する歴史や語源を紐解いていきましょう。 -

破天荒な性格とは?その意味は?
「破天荒」という言葉は、従来の枠組みや慣習を打ち破るような行動や事件などに使われたりします。また、普段は控えめで地味な人が、意外な場面で強烈なインパクトを与えるような様子を表す場合にも使われますが語源には諸説あります。 -

最大限に感動したときに使う「圧巻」とは?
圧巻という言葉は現代でも感動的な場面や風景を目にしたりしたときに使いますが、正しい使い方をしていますか?圧巻の言葉の由来と言葉にまつわるお話をしましょう -

感嘆したときに思わず口にする「流石」の語源とは?
「流れる石」と書く「流石」の語源とは?尊敬を込めた感嘆符でありながら誕生の経緯はある自然現象にあった・・・ -

「お見合い」の歴史と作法を知って幸せな結婚実現
昔は男女の出会いから結婚に至るまで、本人たちの意志に関係なく家同士の話し合いで決められていました。だから突然全く知らない異性とお見合いして、数日も立たないうちに結婚ということがあたりまえでした。 それでもほとんどの男女が夫婦らしく暮らして... -

人妻のことを「奥様」という理由
結婚している女性のことを呼ぶときには、昔から奥様、奥さん、などと呼びます。これは昔から変わっていませんが、私は最近になって現代にはそぐわない呼び方ではないかと思うようになりました。奥様と呼んでいたのは、女性は結婚すると専業主婦になり家を...