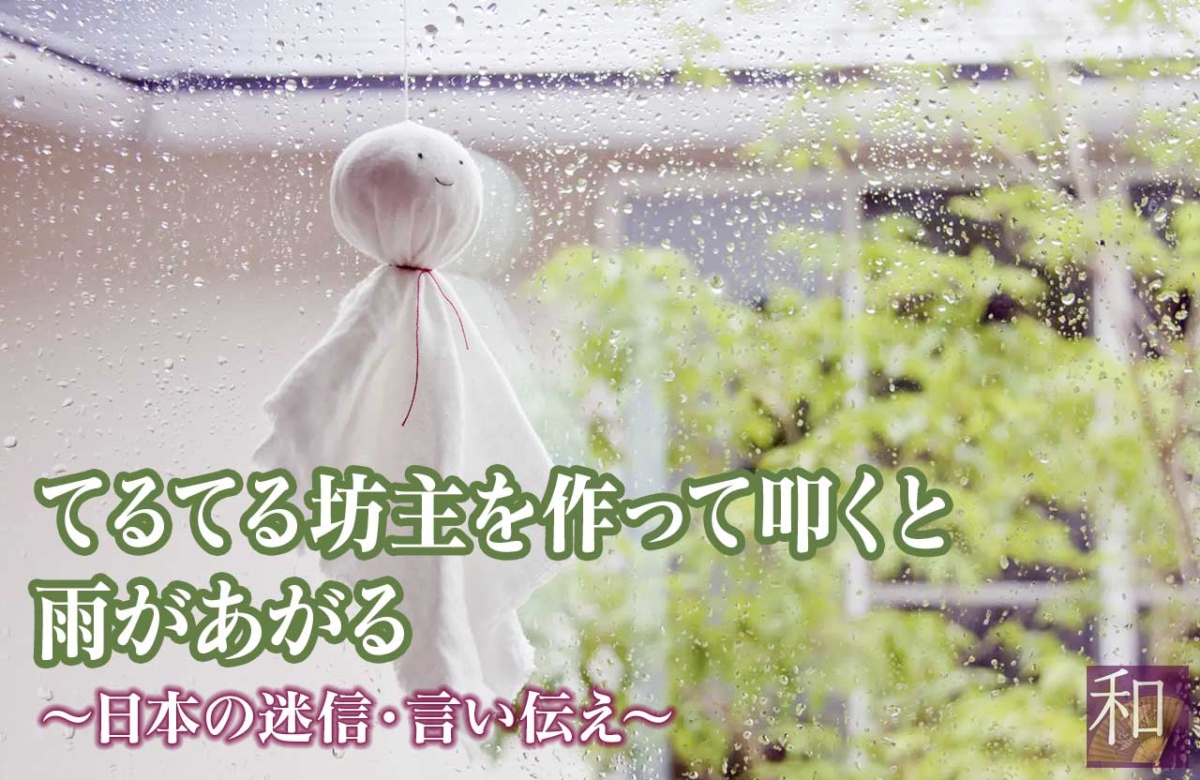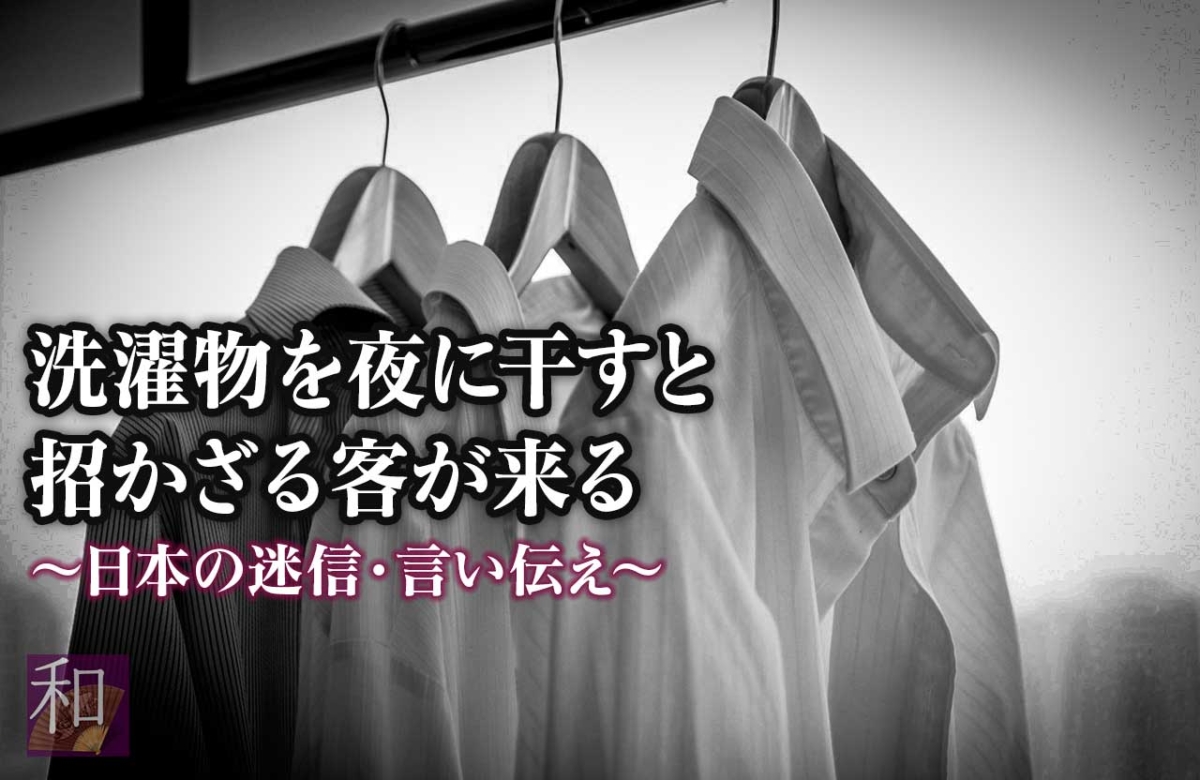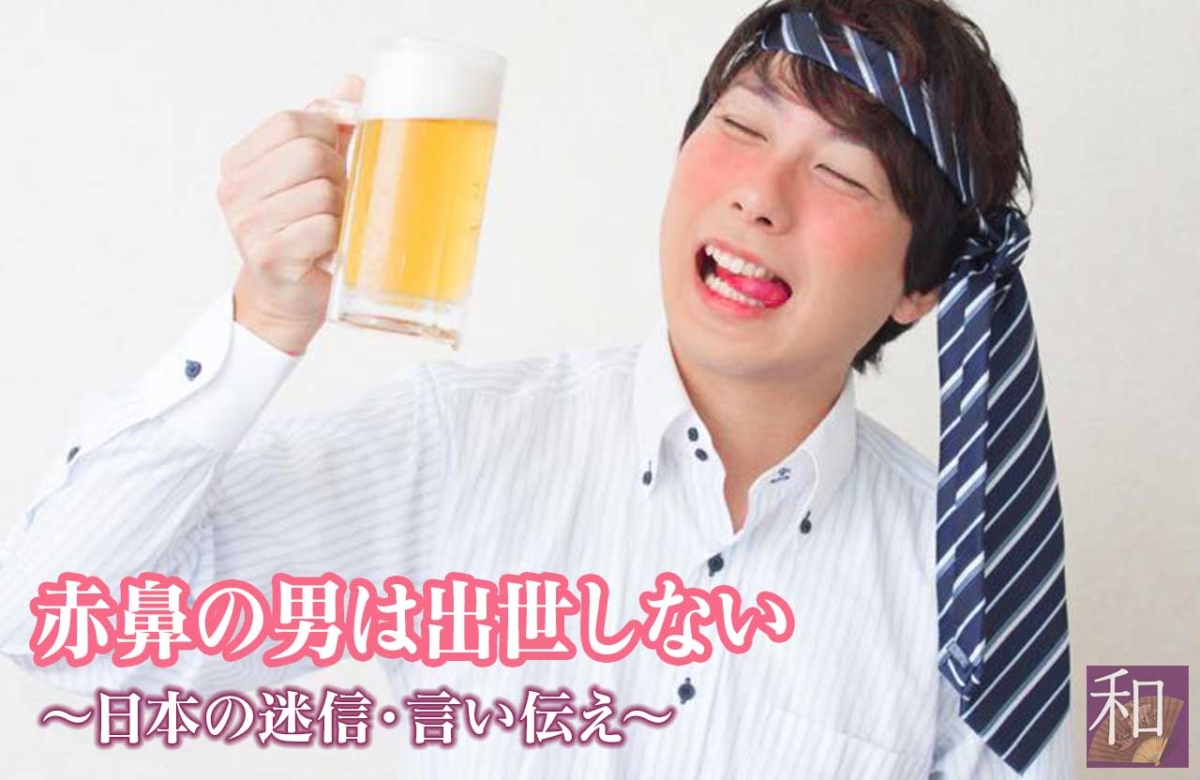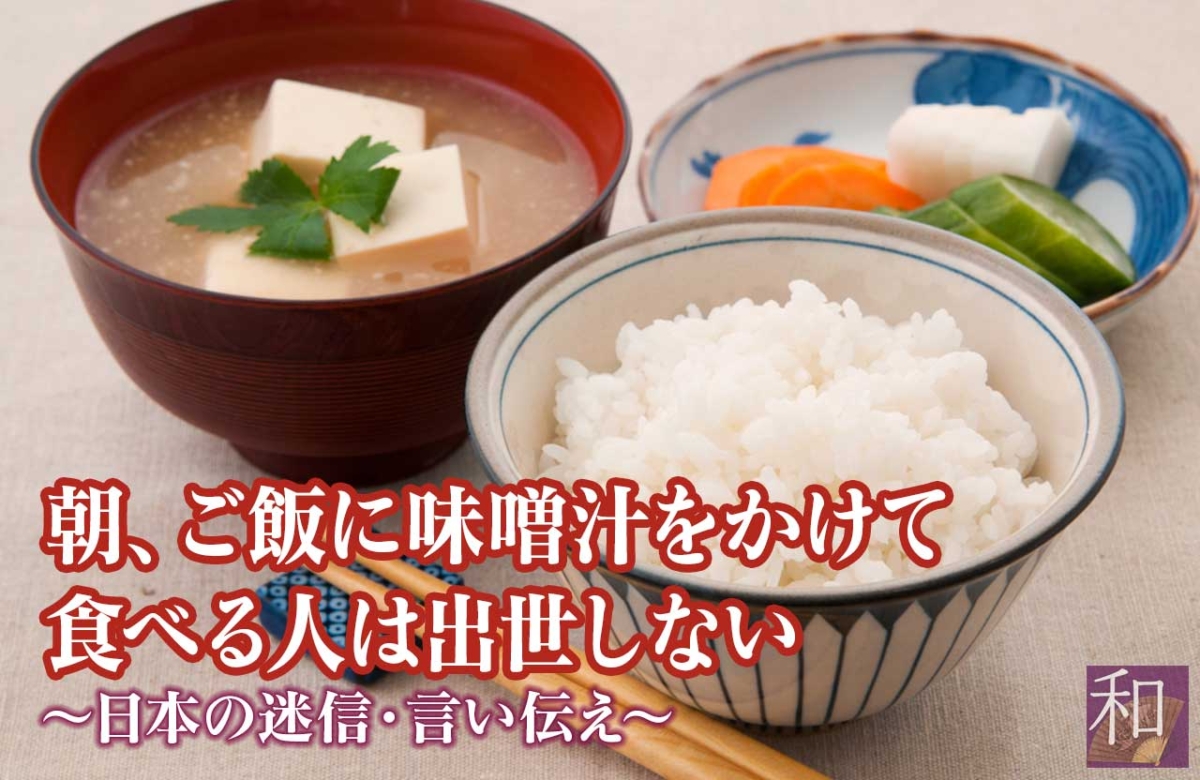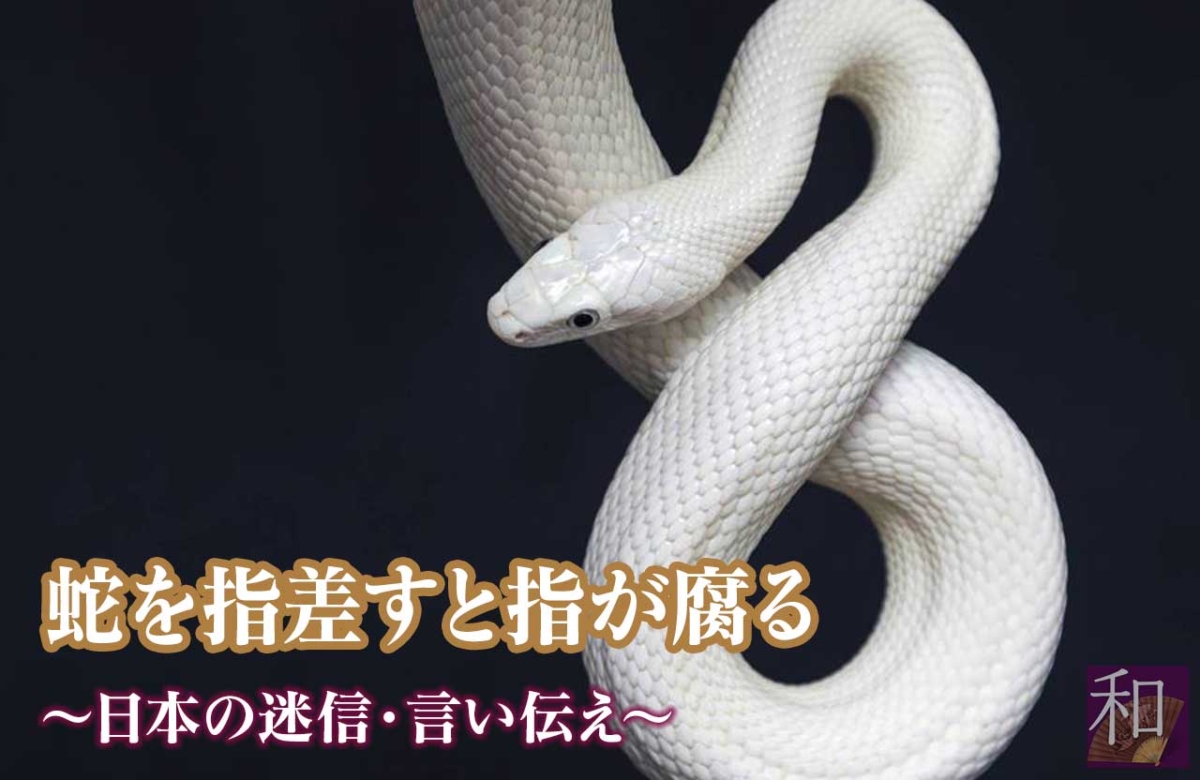新しい記事一覧
-

少年愛は和文化なのか?
戦国武将は小姓を愛し、僧侶は稚児を愛でると、事実は定かではありませんが、少年愛は和文化と言えるのか? -

お祭りは「宵宮」がいちばん盛り上がる理由
宵宮は、祭り本番の前夜祭のことを指します。宵宮は、祭りの前日の夜に行われ、祭りの準備をするための儀式や、神輿や山車を飾るための装飾、神社周辺での祭りのイベントなどが行われます。 私が宵宮をおすすめする理由は、神社の祭りが行われる地域の住民... -

古の媚薬「イモリの黒焼き」は惚れ薬~日本の迷信~
惚れ薬を切望したのは秦の始皇帝が最初? いつの世においても、数多くの女性を手中に収めたいと欲する男性は尽きないようです。最近はSNSや出会い系のアプリを通じて、簡単に多くの女性と知り合える機会が増えて賑わっているようです。ウイルス感染症の影... -

てるてる坊主を作って叩くと雨があがる~日本の迷信~
昔も今も「てるてる坊主」は晴れの神様として健在です。子どものころに、遠足や運動会など、楽しみにしているイベントの前日に雨が降っていると、家の軒先にてるてる坊主を吊るして翌日の晴れを願ったもの。大人になっても、大事な約束が屋外であったり、... -

乱用危険!呪いを成就させる丑の刻参りの作法と代償~日本の迷信~
人が寝静まった深夜の社叢で、カンッカンッと釘を打つ音が暗闇から聞こえてくることがあります。どこの誰かが丑の刻参りに訪れている…音のするほうに静かに近づいていくと、髪を逆立てた女が老木に呪いの藁人形を打ち付けていました。誰を呪っているのか?... -

淫婦(性に淫らな女性)は妊娠しない~日本の迷信~
江戸時代の遊女にまつわる噂 江戸時代にこの迷信が生まれたと伝わっています。淫婦(いんぷ)とは、読んで字の如く、性に淫らな女性、または江戸時代にあった遊郭の女性を指しています。 江戸時代の遊女たちは不特定多数の男性を相手に、身を売っていたの... -

洗濯物を夜に干すと招かざる客が来る~日本の迷信~
洗濯物はよく晴れた日中に干すのが普通ですが、最近では仕事で昼間不在であったり、洗濯物を見られたくないというプライバシーの問題や、衣類の色落ちを心配するなどの理由で夕方から夜に洗濯をする人がいます。 しかし緊急事態宣言下でリモートワークが増... -

お茶占い?茶柱が立つと幸先がいい~日本の迷信~
お茶を飲みたいと思ったときに、急須に入れたお茶を湯呑に注いで飲む様子を想像する人は昭和世代の人かもしれません。今やお茶と言えば、ペットボトルに入ったお茶を連想する人がほとんどではないでしょうか? この茶柱が立った、立たないで一喜一憂してい... -

千羽鶴に願いをかけると叶う~日本の迷信~
病で入院している大切な人へ、災害に合われた地域の方へ、受験の合格祈願に、勝負事の必勝祈願に・・・と、今でも千羽鶴を折って贈る風習は日本人に根強く残っています。 祈りを込めて、一心に折った千羽鶴を用意すれば、願い事は叶うと広く信じられていま... -

赤鼻の男は出世しない~日本の迷信~
鼻が赤い人物といえばピエロを思い出します。なんだか滑稽で、人の顔色ばかり伺っているような道化者。そんなピエロのようなビジネスマンがいたら、外見からはとても出世するようには見えません。赤鼻の男は、貧乏ゆすりと同じように、昔から、将来出世で... -

端午の節句に菖蒲湯に入ると病気にかからない~日本の迷信~
菖蒲湯は、もともとは女性しか入れなかった 菖蒲はアヤメ科の多年草で、初夏には紫や白の美しい花を咲かせます。菖蒲湯は、菖蒲を湯の中に入れて入浴する風習です。かつては、日本全国の数多くの家庭が、端午の節句ともなると菖蒲湯を用意して入浴したもの... -

歯の生え変わりでは、上の歯は縁の下に、下の歯は屋根に~日本の迷信~
意外とこの歯にまつわる風習は、マンションが増えた現代でも細々と生きているようです。 日本では子どもの乳歯が抜けた際は、上の歯の場合は縁の下へ、下の歯の場合は屋根へと投げると、丈夫な永久歯が生えてくると信じられてきました。 西洋では、乳歯が... -

朝、ご飯に味噌汁をかけて食べる人は出世しない~日本の迷信~
一日を元気に健康的に過ごしたいなら、朝食は抜かないことです。朝食も昔ながらのごはんから、今はパンやシリアルなど多様な食事内容になっています。そしてどれにも共通するのが「早く食べられること」です。忙しい朝に、ゆっくりと時間をかけてよく噛ん... -

蛇を指差すと指が腐る~日本の迷信~
蛇を神として崇める日本人 生き物には手足があるものと、勝手に決めつけているから手足の無い蛇を見たときに不気味に感じてしまう。蛇には手足が無いから、動きも独特だし、不気味な動物として古くから恐れられてきました。 しかしその異様な身体のつくり...