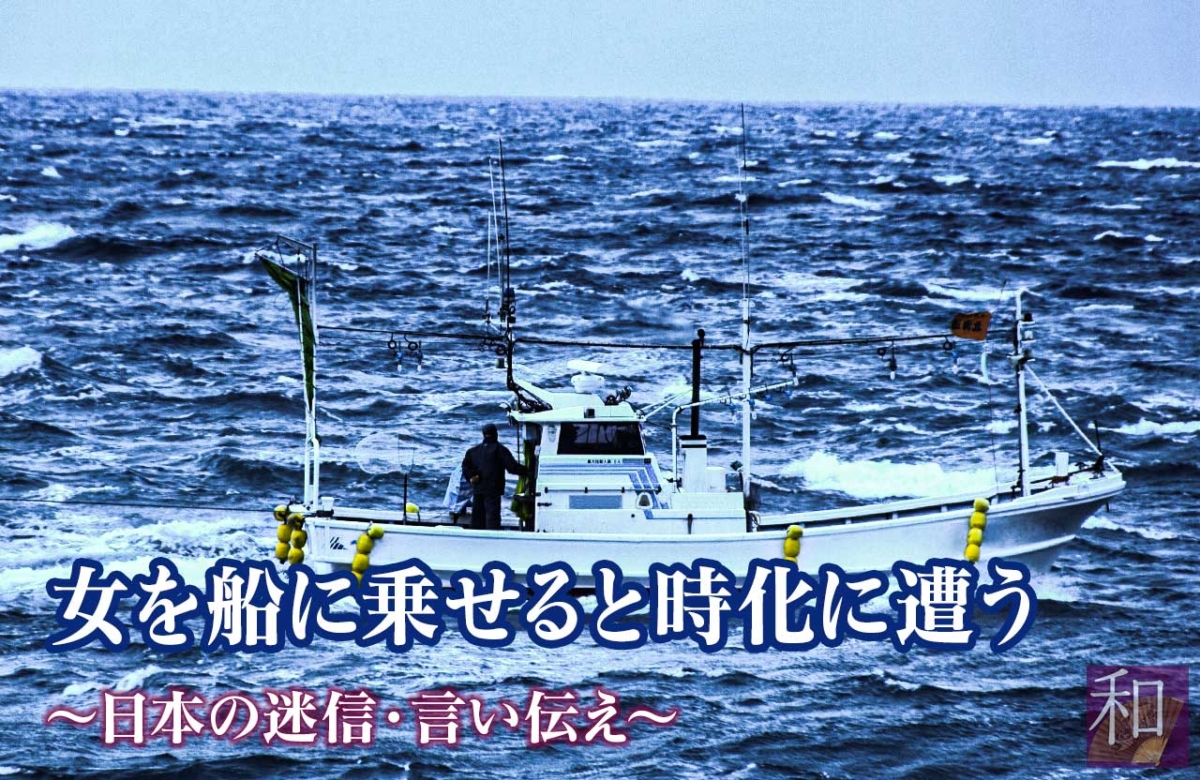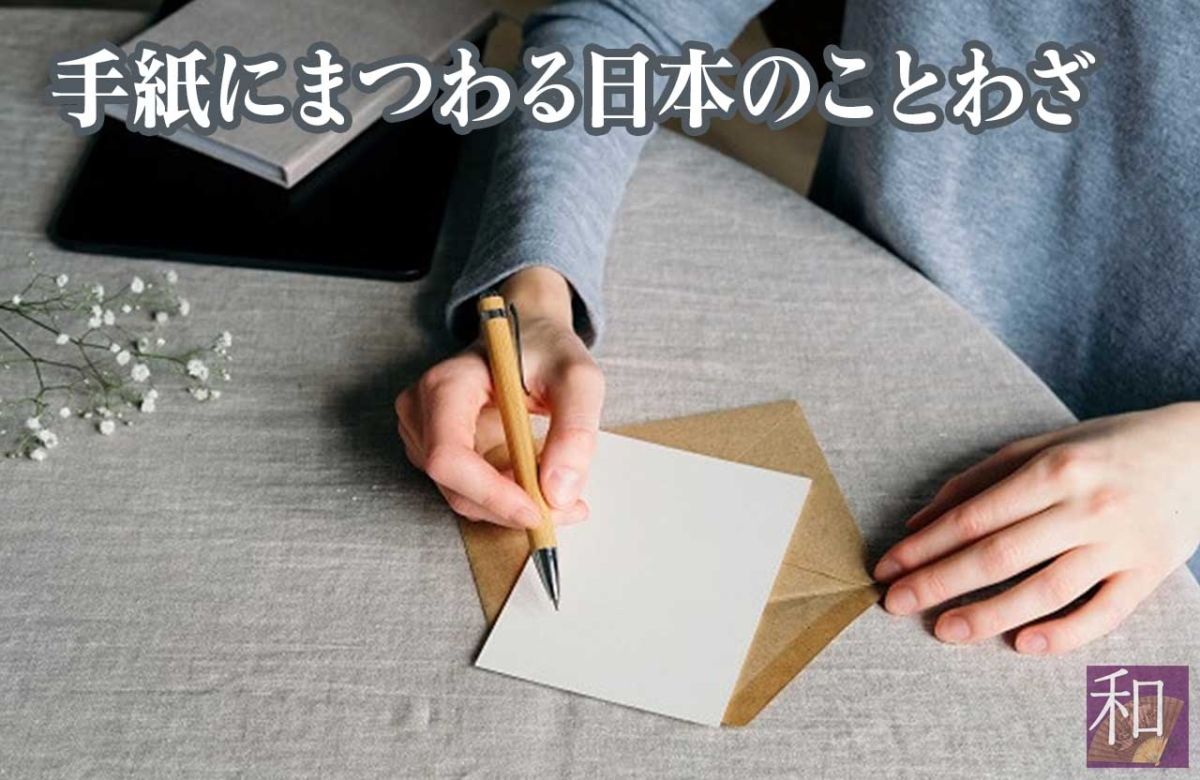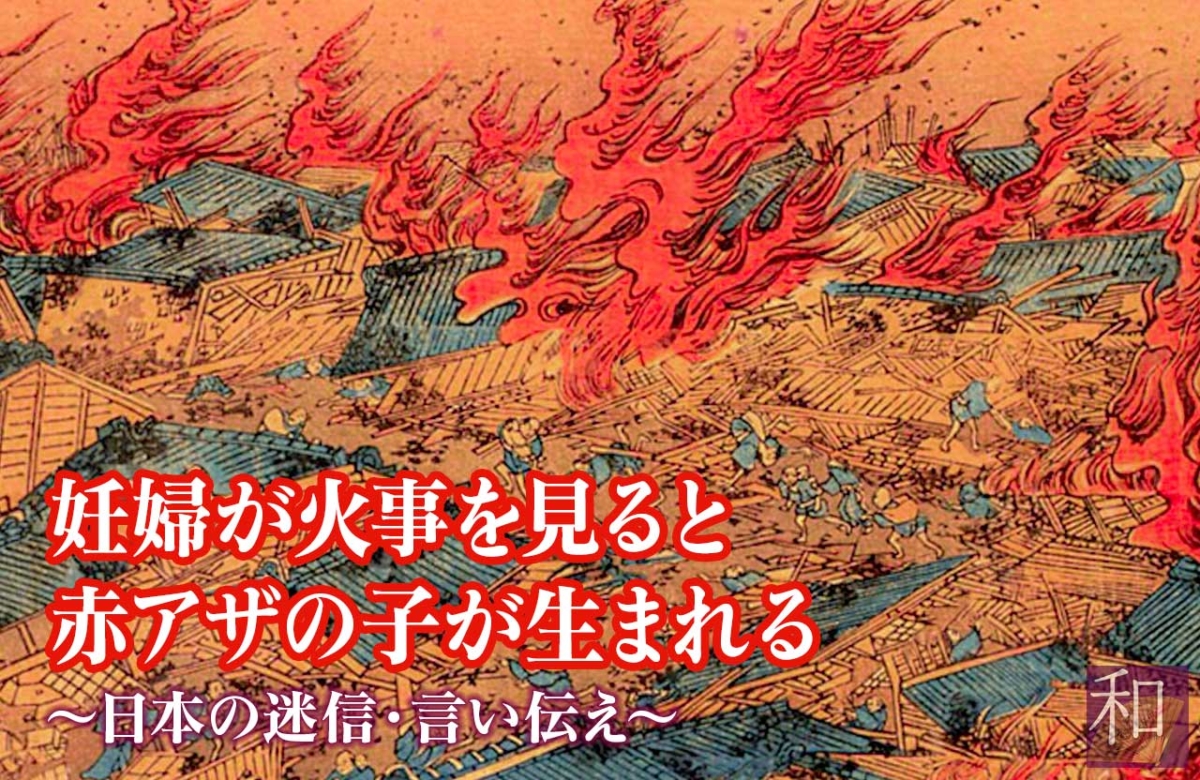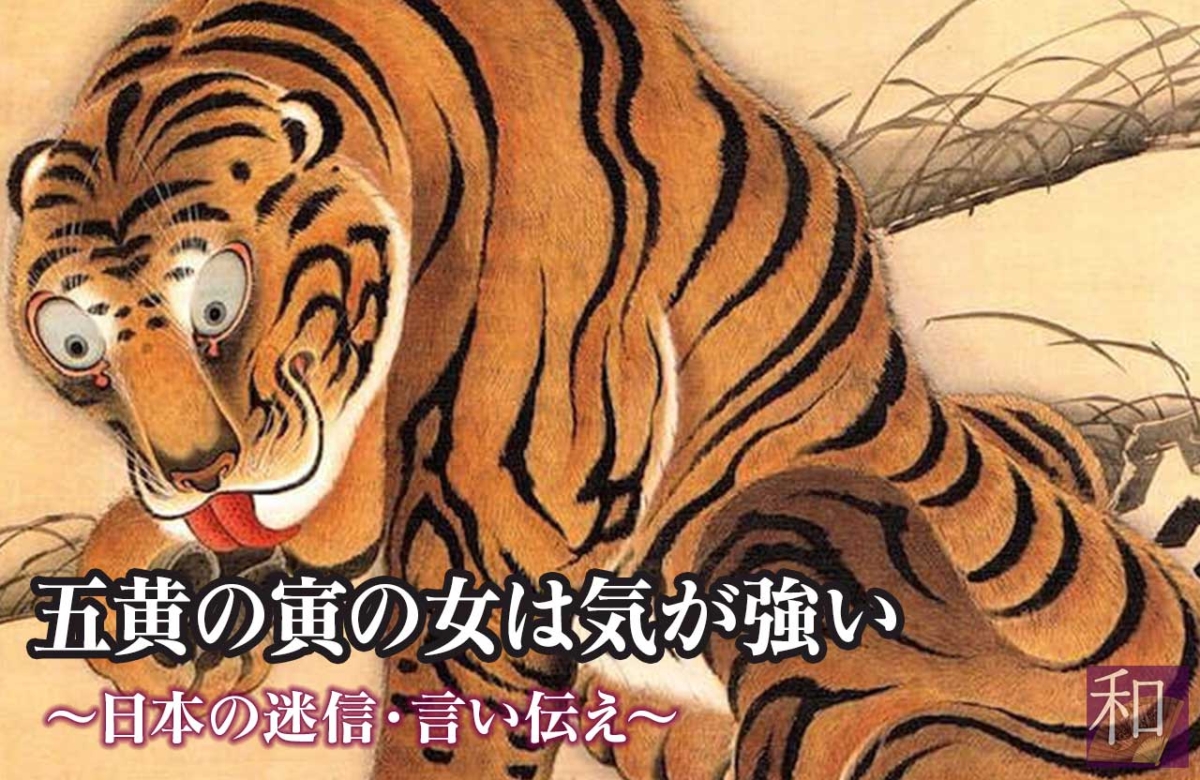2022年1月– date –
-

家の中で傘を差すと運が開けない~日本の迷信~
時代劇などを見ているときに、浪人となってしまった武士が、その日の暮らしを維持するための内職として傘張りをするシーンがよくあります。 この迷信の源は、江戸時代の天下泰平の世に遡ります。剣一本で立身出世の夢が叶った戦国時代であればよかったので... -

火事のときに赤い腰巻きを振ると延焼しない~日本の迷信~
男性には刺激的な赤い腰巻きが、火事場で活躍 腰巻きといえば、着物を着ていた時代まで女性の下着として使われていた布です。昔は、女性の腰巻には特別な力が宿ると信じられていたそうです。 なぜ腰巻きが火事と関係があるのだろう? 昔は完全に真っ裸で... -

爪や髪の毛を火にくべてはいけない~日本の迷信~
時代劇で切腹をした武士の遺髪を、妻や家族に届けられたとき、その死を知るというシーンをよく見ます。 昔から日本人は男女を問わず、髪の毛や爪を大切に扱ってきました。 髪の毛や爪を燃やして処理することは、縁起の悪い行いとされ、燃やすと不幸が訪れ... -

女を船に乗せると時化に遭う~日本の迷信~
山で生計を立てる山師や猟師、海で生計を立てる漁師には昔から仕事に女性が同行することを嫌います。理由は急に天候が崩れて遭難したり、思うように獲物が捕れなかったりするからです。令和の時代になっていろいろな業種で女性が進出するようになっても、... -

手紙にまつわる日本のことわざ
弘法にも筆の誤り 弘法大師(空海)のような書の名人でも、ときには書き間違えることもあるので、どんな優秀な人でも、失敗はあるという意味です。 弘法大師は、平安時代に中国より真言密教をもたらした人。書における高度な技術と教養を持った人でもあり... -

貧乏ゆすりをすると出世できない〜日本の迷信〜
カタカタと近くで物音がすると思っていたら、「貧乏ゆすり」をしている人がいたなんてことはよくあります。「貧乏ゆすり」は落ち着きがなく、近くでやられるとこちらも気になってしまい、集中力がそがれて嫌な気分になります。 人間には誰にも癖というもの... -

沢庵は二切れに限る~日本の迷信~
ポリポリと小気味いい音をたてて食べる沢庵は、とても食欲をそそります。今回はその沢庵・・・というより何切れで食べるかというお話です。 日本人は言葉の語呂の良しあしを特に気にする民族 縁起を担ぐ主人が経営する食堂で、沢庵が白いご飯とともに出さ... -

妊婦が火事を見ると赤アザの子が生まれる~日本の迷信~
赤ん坊の赤アザとは? 昔は赤ん坊のことを、新芽や若葉のように生命力溢れていることからたとえて「緑児(みどりこ)」と呼びました。 しかし、赤アザの子どもと聞いても、あまり聞き慣れないのでピンときません。 医学用語で言うと、血管腫と呼ばれる症状... -

七草粥を食べると病気にならない~日本の迷信~
春の若菜で元気になり邪気を払う 伝統的な食習慣が失われたと言われる現在でも、正月の松飾りがとれる頃には、「春の七草セット」がスーパーなどに並びます。 実際に七草粥を食べる家庭は減っていると思いますが、こういう食習慣が日本にあることは多くの... -

五黄の寅の女は気が強い~日本の迷信~
占いにもあるように生まれた年によって、人の気性が決まってしまうという迷信はいくつかあります。聞いてみるとなるほどよく当たっていると思う内容もあれば、これは自分には当てはまらないなぁと疑問を持つものもあります。また、同じ年同じ月に生まれた...
1