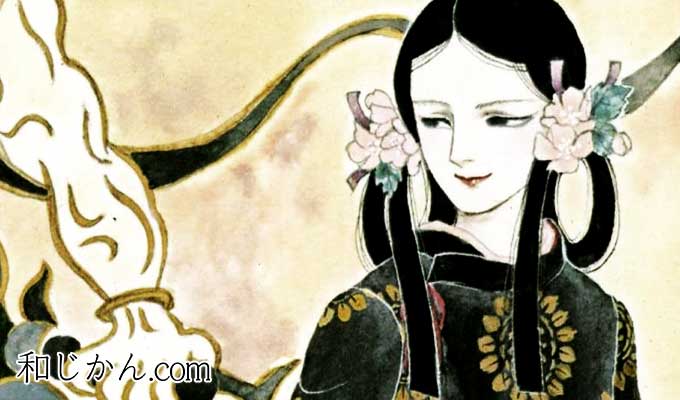行事と伝説– category –
-

お稲荷さんはどうして「五穀豊穣」から「商売繁盛」の神様に変わったのか
お稲荷さんと聞いて、一番最初にイメージするのは、たくさん並んだ赤い鳥居ではないでしょうか。 そして狛犬のようににらみを利かすお稲荷さんの姿。 現代の流行では、キツネ様のお告げで音楽活動をしているというメタルダンスユニット『BABYMETAL』が世界... -

聖徳太子が熱中した仏教と、神仏習合の成り立ち
新札になって数年を経た現代、今の1万円札の絵柄が聖徳太子であったことを知る人もだんだん減っているのではないでしょうか。聖徳太子は、今の歴史の教科書でははっきりと実在した人物として紹介されいません。 時代とともに歴史検証が進んで、聖徳太子と... -

仏教の起源と人間の仏陀が超人になった理由
仏教は日本人にとっては、とてもなじみ深い宗教です。 現代では多くの宗派があります。でも、もともとは1つの経典が日本に伝来した時からはじまったはず。 その多くの仏教の宗派の原点は仏陀であることは、誰でも学校で学ぶことです。 しかし、その存在は... -

「十五夜」「中秋の名月」の奇妙な風習
十五夜は旧暦の8月15日の月夜の行事のことです。月の満ち欠けを基準にしていた旧暦と、太陽の動きを基準にしている現在の暦にはズレが生じるので、毎年9月中旬~10月上旬の間に旧暦の8月15日がやってきます。 旧暦の8月は1年の中で最も空が澄みわたり月が... -

甦りの聖地、熊野神社と熊野信仰
熊野神社といえば紀伊半島にある熊野本宮や熊野速玉大社、熊野那智大社がすぐに思い出されます。交通インフラの発達した現代においても、三社へお参りするのは結構たいへんです。それだけに到着してお参りしたときの何とも言えない幸せな気持ちは、ここな... -

神明社は各地を明るく照らす「お伊勢さん」
稲荷神社や八幡神社と同様に伊勢神宮の分社も全国にあります。西日本より東日本に多く、「お伊勢さん」と呼ばれて地域の人々に親しまれています。各地の神明社には、天照大神がその地に飛んできたことに由来して神社を創建したという伝承が残っています 【... -

諏訪神社、奇祭と神々の力比べ
6年に一度、御柱と呼ばれる4本の杭を立てる御柱祭が行われる諏訪神社は、その1度見たら忘れられない祭りが印象的です。 諏訪神社の祭神は建御名方神(タケミナカタノカミ)です。 大国主命の子であり、狩猟の神、「山の神」といわれます。ただし、「ミナカ... -

大漁旗を意味する海の神が八幡神社として、武勇の神になった理由
全国的に多い神社といえば、お稲荷さんが1番ですが、次に多い神社は「八幡さま」と親しまれている八幡神社ではないでしょうか。八幡神(はちまんしん やはたのかみ)は、神社では誉田別尊(ほんだわけのみこと)、あるいは諡号(死後の贈り名)の応神天皇... -

豪快な張り子が踊る「ねむり流し」。青森ねぶた祭りの起源と伝承(青森市)
巨大で豪快な武者姿の張り子が町を練り、「ラツセラー ラッセラー」の掛け声を張り上げて大勢のハネトが跳ねる。「ねぶた祭り」というと、8月1日~7日にくり広げられる青森市の祭りが有名だが、実は「ねぶた」とは東北地方、特に青森県各地で広く行われて... -

最も身近な人生の相談役となる氏神様の種類と由来
伊勢神宮、春日大社など神社と言えば有名なところのほうが御利益はあるといいます。でも1番大切にしなければならいのは、自分が住んでいる地域の氏神様です。つねに身近に存在し、身の回りで見守ってくれている神様こそ、大切にしなければなりません。 お... -

お稲荷さんで親しまれる稲荷神社と秦氏の関係
商売の神様といえばお稲荷さんとして親しまれている稲荷神社です。暮らしと仕事に密接に関係している御利益が期待できるので、全国に点在し、神社の中では1番多い。しかしその起源は、全く違うところにあった。 【稲荷神社の発祥は古代豪族、秦氏の守り神... -

お祭りの醍醐味、おみこしと縁日の由来
ワッショイワッショイと町内を回ってくるおみこしは、世代を問わず胸が高鳴るものです。子供の頃はみんなでお祭りのはっぴを着て、おみこしを担ぐ大人を見てとても憧れたものです。おみこしがあるとお祭りという行事が「神事」であると意識することができ... -

ご飯は盛るものか、それともよそうもの?ご飯の作法とは
ご飯を炊飯器などからお茶碗に入れる時のことを、「盛る」と言うのか、「よそう」と言うのか、どちらが正しいのでしょうか?大盛り中盛りという言葉があるので、やっぱり「盛る」が正しいのか? 【ご飯を「よそう」の粋な語源とは?.】 昔から日本の家庭... -

神々の魂を浄める大松明。那智の火祭りの起源と伝承(和歌山県 熊野那智大社)
今や伊勢神宮にならぶパワースポットとして名高い熊野地方。春から秋にかけて、熊野古道をめぐりながら、古の時を歩く旅が流行しています。伊勢とは違って、ちょっと不便な所にあるために、どんな交通手段を使っても、目的の場所に到着するためには、それ...