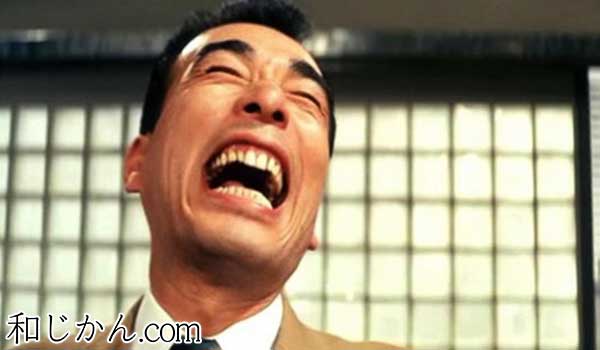2015年7月– date –
-

「とばっちり・ちゃらんぽらん・くだを巻く」ちょっと迷惑な様子を表現した日本語の語源
社会生活を営んでいると他人との絡みで迷惑を被ったり、逆に迷惑を掛けることになったりすることがあります。そんな時につい口をついて出てしまう言葉や、そんな様子を表現する言葉が日本にはあります。普段何気なく使っている言葉でも、その由来を知ると... -

「黄昏(たそがれ)」の語源と夕陽の謎
夕方、太陽が沈んで徐々に暗くなっていくほんの一時の間、その日の出来事や想いを振り返りつつ、ただその場の空気を味わう。明日はどんな1日だろうか?今日に満足できただろうか?実に様々なことを想ったり、逆に何も考えずに無心で空を眺めていたり、この... -

お葬式のしきたりと和の作法(3)
お葬式に伴う風習として、お布施や香典などお金にまつわるものがあります。人付き合いが希薄になってきている風潮の現代では、金額に迷うことも多いようです。お葬式自体も最近は業者任せになっていることがほとんどで、病院から葬儀会社に連絡が行って、... -

うんこにおまる、とんちんかん、普段疑問に持たない言葉の語源は面白い
色や臭いが健康のバロメーターと言われる「うんこ」という言葉。文字にするとなんだか可愛らしいですが、普段から何気に使っている言葉の語源を調べると面白い。またトイレに一人で入れなかった幼い頃に使っていた「おまる」。語源はきっとその丸い形から... -

ご飯は盛るものか、それともよそうもの?ご飯の作法とは
ご飯を炊飯器などからお茶碗に入れる時のことを、「盛る」と言うのか、「よそう」と言うのか、どちらが正しいのでしょうか?大盛り中盛りという言葉があるので、やっぱり「盛る」が正しいのか? ご飯を「よそう」の粋な語源とは?. 昔から日本の家庭に見... -

女人禁制と女の穢れの関係
今は山ガールで賑わう富士山も江戸時代までは女人禁制でした。今でも女人禁制の山があり、お祭りのしきたりなどが残っている地域があります。女性差別の古い風習に捕らわれてはいけないと声を荒げる人々もいるようですが、日本の歴史を振り返ると女性の天... -

お葬式のしきたりと和の作法(2)
お葬式の準備が整うと、最初にお通夜が行われます。親類縁者、知人友人、仕事の関係者などに連絡がいき、参列できる人のみが急いでやってこられます。最近では場所や費用、手間などの理由で、お葬式が全て終わって落ち着いた段階で、連絡だけしておくとい... -

お葬式のしきたりと和の作法(1)
人間は生まれてから死ぬまでの間に、多くの儀式を経験します。冠婚葬祭はその代表的なものですが、なかでも「慶事と弔事が重なるときは、弔事を優先しろ」といわれるくらい、死者を弔い、冥福を祈ることを重要と考えてきました。 死者を弔うにあたっては、... -

手土産の選び方と渡し方の作法
相手のお宅に訪問するのに、手ぶらで行くというのも気持ちが落ち着かないものです。ちょっとしたものでいいので、手土産を持って行く方がいいかもしれません。一般的に手土産は、お菓子やお酒など<消えてしまうもの>がいいと言われています。訪問先の相... -

「ケチ・油断・ろくでなし」偏見,嫌味,悪口を連想する日本語の語源
感情にまかせて、つい口をついて出てしまう言葉や、心に浮かぶ言葉が私たちにはあります。日本人はとても感情豊かで、それを言葉に表現するのもとても上手です。その言葉の語源を紐解いていくと、その言葉に秘められた意外な真実を知ることができるかもし... -

神々の魂を浄める大松明。那智の火祭りの起源と伝承(和歌山県 熊野那智大社)
今や伊勢神宮にならぶパワースポットとして名高い熊野地方。春から秋にかけて、熊野古道をめぐりながら、古の時を歩く旅が流行しています。伊勢とは違って、ちょっと不便な所にあるために、どんな交通手段を使っても、目的の場所に到着するためには、それ...
12