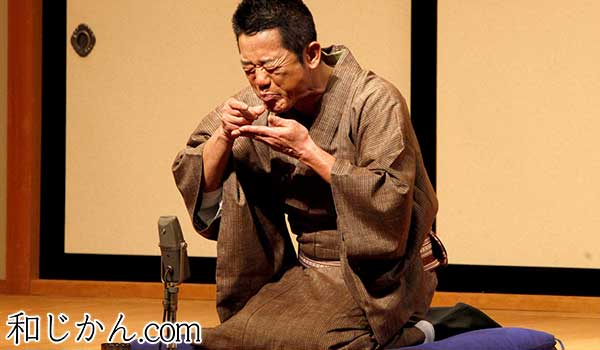2015年6月– date –
-

暮らしに密着した夏のお祭りの起源と伝承
穏やかな春が過ぎて、梅雨が明ける頃、夏から秋にかけての大きなお祭りが各地で催されます。京都の祇園祭などはその代表例ですが、日本の夏は昔から疫病が流行ったり、天災などの自然災害に見舞われたりと何かと災いの多い季節。 だから神に祈る鎮守の意味... -

人付き合いの作法。他人の領域を侵さない「腹五分のおつき合い」とは?
他の地方の人から見ると関西人は、他人の領域にずかずかと入ってくると言われますが、実はそうではありません。昔から貴族文化が発展していた京都、商業が盛んであった大阪、宗教文化の拠点であった奈良など、関西人は人と人との交流には特に気を遣ってい... -

厄年と日本の神々
人生の善し悪しを左右する縁起の話をする上で欠かせないのが「厄年」の存在です。人間生きていくなかで、ずっと全力疾走はできません。時々休憩を入れて体調を整えないと、大きな事故に繋がりかねません。それを人生の節目とし、厄年というものが考えられ... -

手締め、清めの塩、鬼門、普遍的な縁起担ぎの由来
普通に生活をしていると、それが縁起担ぎの行為であると知らずに行っている習わしがたくさんあります。例えば手締めなどがそうです。お祝いの席で景気づけにおこなっていたり、場を締めるためにおこなっているように思いますが、これも古代の宗教的な慣習... -

身近な神様と願掛けの作法
人は何かの節目に立つとき、最後は神頼みとばかりに願掛けをおこないます。近所の神社へお百度参りをしたり、ダルマや招き猫を側に置いて、来たるべき福を待ち望んだり、絵馬に願いを書いて境内に祀ったり、つねに神様と共にあると考える日本人ならではの... -

日本の縁担ぎの風習の由来
結婚や就職など何か人生の転機となる日は、できるだけ良い日を選ぼうとするのはいつの時代でも同じです。例えば大安を選んだり、仏滅を避けたりなどです。それらは化学的な根拠のないものですが、昔から日本人はこの縁担ぎの風習を大切に受け継いできまし... -

訪問先の玄関前で恥をかかない訪問時の作法(2)
到着は「ちょっと遅れて」がちょうどいいと思います。訪問する際は「時間厳守がいちばん」と思ってはいませんか?仕事であればそれでいいと思います。儀礼的な訪問も相手によっては、仕事の1部だと言えなくもないですが、相手の勤務先に訪問するのと相手の... -

駄酒落は日本語だからこそ生まれた日本の文化です
「ほとんどの日本人は、学校で何年間も英語の授業を受けているのに、英会話ができない」とよく言われる。たしかにそうかもしれない。そもそも学校で習う英語は、実用的な英会話ではなく、あくまでも試験対策用の英語なので、学生を批判するわけにはいけな... -

訪問時の作法(1)お伺いする前の常識
社会人になると会社の上司や同僚、または取引先の方などのお宅に訪問する機会があるかもしれません。どんなに親しい間柄であっても、最低限の作法は意識して伺いたいものです。そんなに堅苦しく考える必要は無いのですが、相手が気分を害することのないよ... -

「日本」の正しい呼び名、読み方を知ってますか?
ニホン、ニッポン、ジャパン、ジャポン、ヤーポン・・・日本の呼び名はたくさんあります。これも最近のことではなくて、ずいぶん昔からいろいろな呼び方があったようです。その由来を探ってみましょう。 英語表記はなぜ「Japan」と書くのだろう? あまりにも... -

神様にお供え物をする際の儀式が礼儀作法になった
日本語の由来を知りたいと思えば、漢字などの文字の変遷を見ていくと、よくわかります。礼儀作法の「礼」は、旧字体では「祀」と書きます。「示」は神様を表わし、「豆」は神様にお供え物をするときの台のこと、その上の「曲」はお供え物のこととされてい... -

「遠慮」とは相手の心の向こう側までも配慮すること
日本人はどんなに親しい間柄でも「遠慮」することがよくあります。奥ゆかしさを感じる表現ですが、何かを断る際にも「遠慮」という言葉で遠回しに意思表示する際に使ったりしています。海外の人から見ると、日本人の遠慮という行為は理解しにくいようです...
1