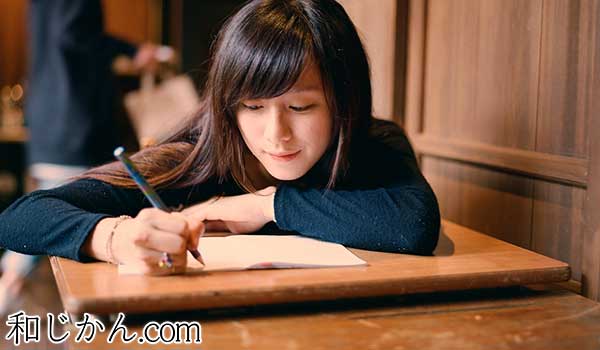2014年9月– date –
-

手紙の作法(手紙やメールで使ってはいけない言葉がある)
日本は言霊の国であり、言葉の持つ意味に対してとりわけ敏感なため、手紙のなかでも忌み言葉を避けてきました。 手紙の禁忌言葉 日本は言霊の国であり、言葉の持つ意味に対してとりわけ敏感なため、手紙のなかでも忌み言葉を避けてきました。 ◎結婚、出産... -

手紙の作法(時候の挨拶と季節の手紙)
四季の変化に富んだ日本では、季節に対する感性が磨かれていきました。日本人は季節の移り変わりにとりわけ敏感で、手紙でも、四季折々の情景を折り込んだあいさつで始めるのが、習わしとなっています。現代はその感性も鈍っているのと、機械変換で言葉の... -

「道楽」とは仏道で得た悟りの楽しみのこと。道楽の語源
道楽息子は放蕩息子ともいうように、怠け者や身持ちのよくない人間をさします。「女道楽」や酒、賭け事にうつつを抜かすのは「道楽者」。このように「道楽」という言葉は、好ましくないニュアンスで使われることも多い。 道楽の語源 本来は仏教の言葉で、... -

手紙の作法(頭語と結語)
日本では、手紙文を書く際に、頭語(冒頭に書く言葉)と結語(結びに書く言葉)を入れるのが一般的です。例えば、「拝啓」で始めて、「敬具」で締めるのが頭語と結語の組み合わせです。 どうして「拝啓」で始めて「敬具」でしめるのか? 「拝啓」は、「拝... -

手紙の作法(表書きと裏書き)
現在のように電話やインターネット、ファクシミリがなかった時代には、手紙が唯一の伝達手段だったため、古くから手紙のやりとりが重視されてきました。とくに礼儀を重んじる日本人にとって、手紙は書式をはじめ、文体、言葉遣いなどにも、細かな心配りを... -

家を建てるときに行う日本の風習「地鎮祭」「棟上式」
日本は古くから八百万の神に対する信仰が根付いています。だから家や建物を新築する際には、その土地に宿る神々の許しを請い、末永く守ってもらえるように祈願する祈祷を行います。そんな家の建築にまつわる風習を解説します。 何の目的があって地鎮祭を行... -

古から人の生活に欠かせない「鶏」は「庭つ鳥」の意味
田舎に行くと朝、どこからともなくコケコッコーの声で目覚めることがあります。そうで無くても日常的に卵を食べたり、卵を使った料理を食べている私たちにとって、鶏は鳩と雀と同じくらい身近な鳥類です。 そんな鶏と日本人の関わりを語源の観点で調べてみ...
1