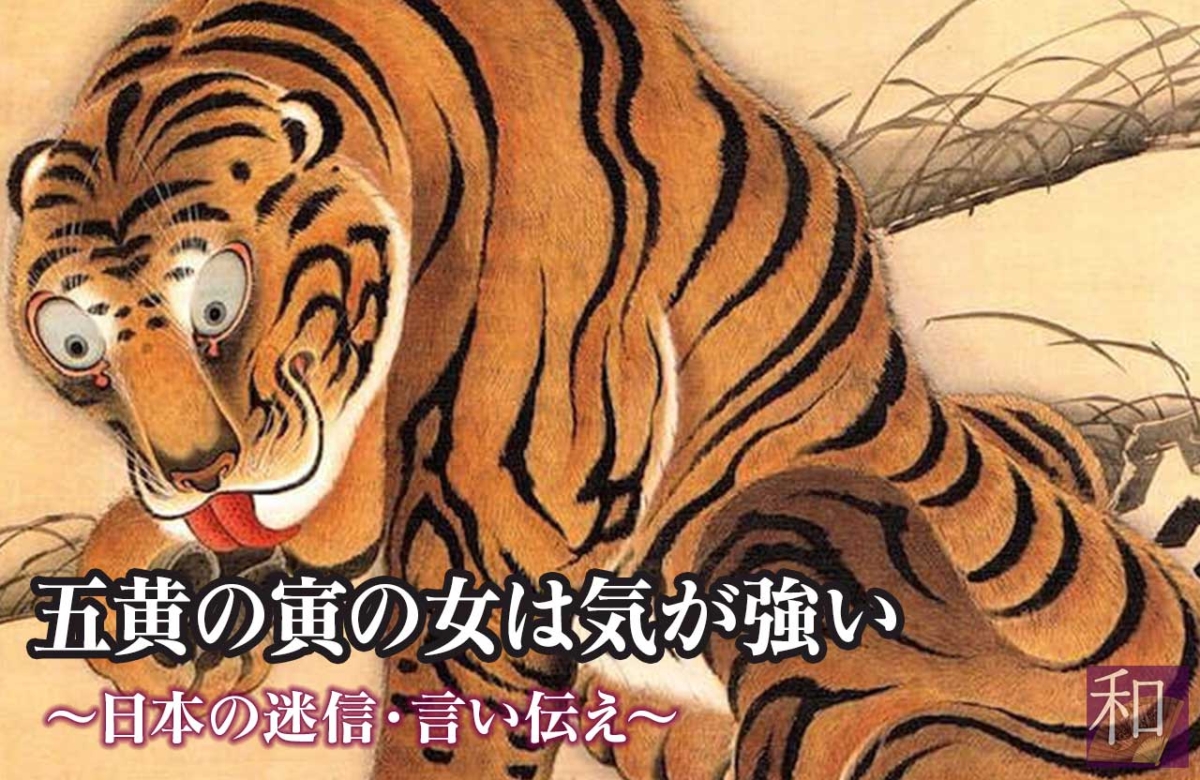新しい読み物
-

神懸かりと禊の儀式
神憑りなど、この世に存在しない霊的な者の魂を自分に憑依させる行為は、日本だけでなく世界各地にあります。 そして「神懸かり」は「禊」の儀式とは切り離すことはできません。 その意味や由来と、現代に生きる私達が守っていかなければならない伝承を考えてみましょう。 -



「松花堂弁当」は絵の具箱から生まれた懐石料理
お弁当といえばキャラ弁や愛妻弁当、幕の内弁当など多様な種類があります。実はお弁当の代名詞といえば「松花堂弁当」といわれます。 松花堂弁当は、中に十字形の仕切り… -



樹木伐採時の「木霊鎮め」の神事とは?
「木霊鎮め」とは、樹木伐採の際に、神仏に感謝の意を表し、また、樹木や森林の霊を慰めるために行われる神事のことです。現在も行われる木霊鎮めの作法や由来を調べてみました。 -



日本のお祭りの起源と伝統行事
迫力のあるお神輿やたくさんの屋台が並び、人が賑わうお祭りはとても楽しい。そのお祭りの本来の意味や起源はと気になりませんか? -



御神木は神様の依代であり古代アニミズムの象徴
「御神木の画像をスマホの待ち受け画面に設定すると幸運になる」という都市伝説が流行っているようですが日本各地には「御神木」と呼ばれる巨樹や老樹が神社や寺院などにありますが、なぜこれほどまでに地域に敬われ崇拝されているのでしょうか? -



拍手の意味は神様を尊び、招くこと
古代日本では、拍手は神々を招き入れるための儀式として行われることが一般的でした。神々を迎え入れることで、豊穣や平和、幸福を願い、神々の加護を受けることが期待されていました。このような文化は、現代の日本においても拍手をする習慣は暮らしの中に息づいています。その意味と由来を調べてみました。
日本語と語源
-



神社で御神酒が奉納される理由
御神酒は、神道における神事の一環として奉納されます。神社によっては、毎日の祭儀で御酒を供える場合もありますし、特別な祭りの際にのみ御神酒を供える場合もありますが・・・ -



日和見主義、小春日和の「日和」とは?
日和という言葉には、のんびりしたのどかな印象を与えます。その印象を天候に例えたり、人格に例えたり、様々に使える便利な言葉です。この日和という言葉にはどんな意味が含まれているのでしょうか? -



困難に直面しても「火中の栗を拾う」意味とは・・・
「火中の栗を拾う」という言葉は、危険や困難を冒して得ようとすることを表す日本の慣用句です。他人がやりたくない、またはできないような危険な仕事や困難な状況に対して自分自身が挑戦することを指します。でもこの場合の行動は失敗に終わるケースがほとんどだと言われています。それはなぜでしょうか?この言葉の由来が説明しています。 -


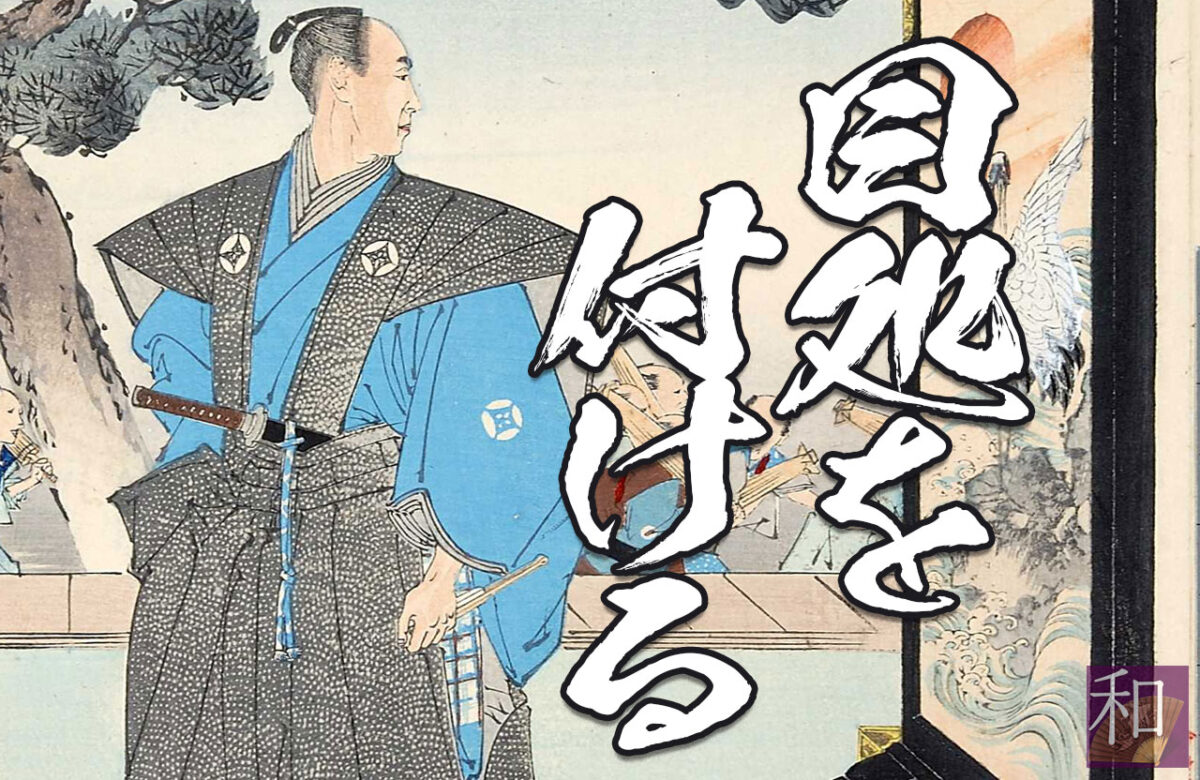
「目処を付ける」の意味と使い方
例えば仕事に一区切り付けることを目処を付けるといい、目標設定をする際にも何日までに目処をつけようといいます。この目処をつけるという言葉にはどんな由来があるのでしょうか?リモートワークでなかなか仕事の区切りがつけられないリモートワーカーにおすすめしたい言葉ですね。
風習としきたり
-



「松花堂弁当」は絵の具箱から生まれた懐石料理
お弁当といえばキャラ弁や愛妻弁当、幕の内弁当など多様な種類があります。実はお… -



神懸かりと禊の儀式
神憑りなど、この世に存在しない霊的な者の魂を自分に憑依させる行為は、日本だけでなく世界各地にあります。 そして「神懸かり」は「禊」の儀式とは切り離すことはできません。 その意味や由来と、現代に生きる私達が守っていかなければならない伝承を考えてみましょう。 -



樹木伐採時の「木霊鎮め」の神事とは?
「木霊鎮め」とは、樹木伐採の際に、神仏に感謝の意を表し、また、樹木や森林の霊を慰めるために行われる神事のことです。現在も行われる木霊鎮めの作法や由来を調べてみました。 -



御神木は神様の依代であり古代アニミズムの象徴
「御神木の画像をスマホの待ち受け画面に設定すると幸運になる」という都市伝説が流行っているようですが日本各地には「御神木」と呼ばれる巨樹や老樹が神社や寺院などにありますが、なぜこれほどまでに地域に敬われ崇拝されているのでしょうか?
迷信とことわざ
行事と伝説
-



「神主」と「巫女」の仕事
神社に行くと神主さんや、巫女さんの姿をよく見かけます。 ご祈祷や行事がある時に… -



神懸かりと禊の儀式
神憑りなど、この世に存在しない霊的な者の魂を自分に憑依させる行為は、日本だけでなく世界各地にあります。 そして「神懸かり」は「禊」の儀式とは切り離すことはできません。 その意味や由来と、現代に生きる私達が守っていかなければならない伝承を考えてみましょう。 -



樹木伐採時の「木霊鎮め」の神事とは?
「木霊鎮め」とは、樹木伐採の際に、神仏に感謝の意を表し、また、樹木や森林の霊を慰めるために行われる神事のことです。現在も行われる木霊鎮めの作法や由来を調べてみました。 -



日本のお祭りの起源と伝統行事
迫力のあるお神輿やたくさんの屋台が並び、人が賑わうお祭りはとても楽しい。そのお祭りの本来の意味や起源はと気になりませんか?